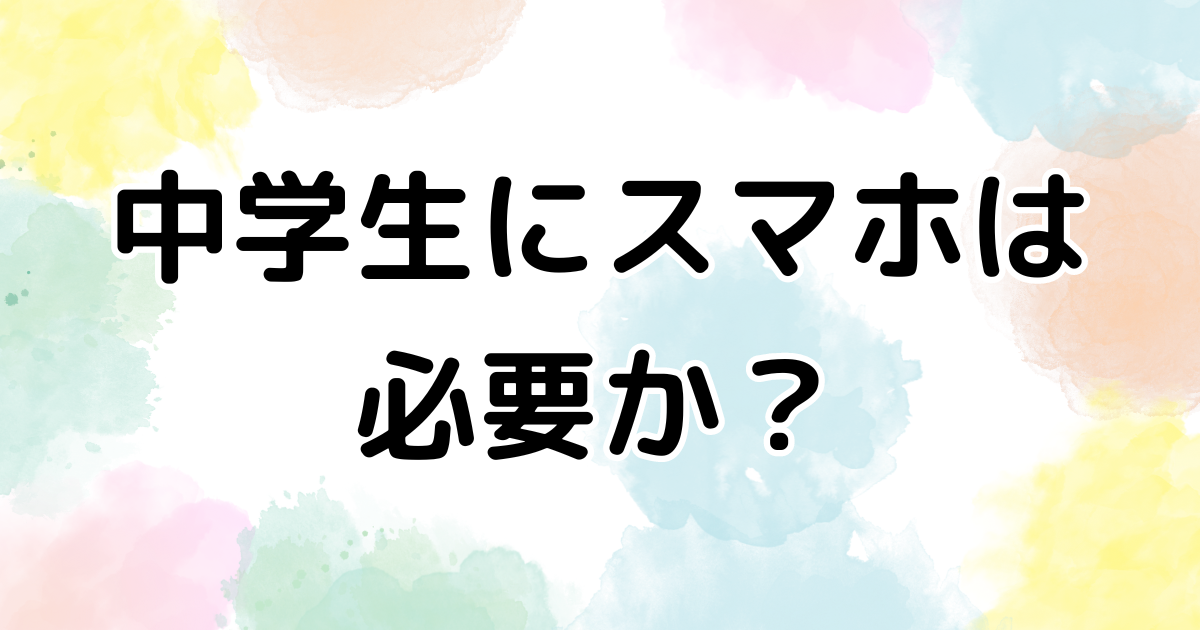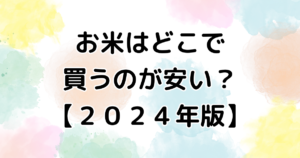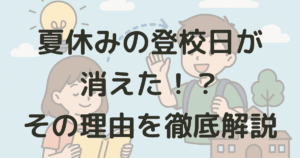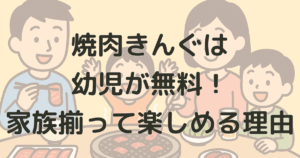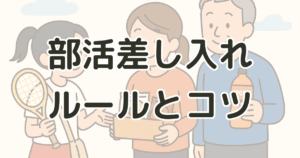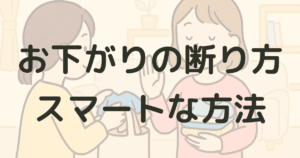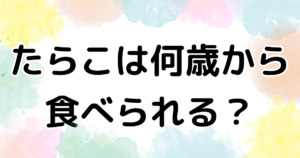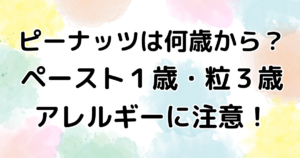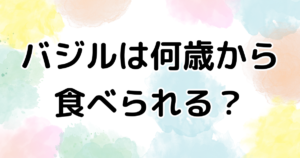お子さんがスマホを使っているかどうかは、親にとって重要な問題です。
友達がスマホを持っている中、いつ子どもにスマホを持たせるべきか、本当に必要かどうかを決めるのは難しいですよね。
高校生になるとスマホを持つのが普通になり、バイトをして通信費を自分で払うこともできるようになります。
義務教育が終わると、保護者はスマホが本当に必要か、インターネットの危険から子どもを守れるかなど、いろいろ心配するものです。
この記事では、中学生にスマホが本当に必要なのか、そのメリットとデメリット、発生するかもしれないトラブルについて解説します。
スマホは便利ですが、中学生にとっての良い点と気をつけるべき点をよく理解しておくことが大切です。
小中高生のスマホ所有率
まず、小学生から高校生までのスマホ所有率がどの程度か、最新の調査結果を見てみましょう。
内閣府が行った、2016年11月から12月にかけて10歳から17歳の子ども5000人を対象とした「青少年のインターネット利用状況調査」の初期報告によれば、スマホの所有率は以下のようになっています。
- 小学生:27.0%
- 中学生:51.7%
- 高校生:94.8%
これにより、中学生のほぼ半数がスマホを持っていることが分かります。
スマホは中学生に必要?
スマホを持つことを禁じている学校もありますが、それは中学生にスマホが不要だと考えているように見えるかもしれません。
しかし、実際には多くの中学生が、友達が持っているから自分も持ちたい、持たないと仲間はずれになるなど、さまざまな理由でスマホを欲しがっています。
この記事では、中学生にスマホを持たせるメリットと、それに伴う潜在的な問題点を考えながら、この年代でスマホを持つことの必要性について総合的に検討していきます。
中学生にとってのスマートフォンのメリット
この部分では、中学生がスマートフォンを使う際のメリットに焦点を当てます。
使い勝手の良さ
スマートフォンは非常に便利なツールです。ウェブ検索、美しい画像の閲覧、メモの取り方、ゲーム、計算機能、地図の利用など、多様なアプリを活用することで日々の生活がより快適になります。
最初にスマートフォンを使った時の驚きや感動は、多くの人が経験することです。
保護者が感じるその便利さは、中学生にも等しく提供される重要なツールです。
情報量の多さ
インターネットは情報で満ち溢れており、最新ニュースや流行りのトピックスへ素早くアクセスすることができます。
たとえば、当日発生したニュースの詳細や有名人の最新情報をすぐに調べることができます。
これは、情報を得る範囲を大きく広げてくれます。
かつては新聞や雑誌を通じてしか情報を得られなかった時代とは異なり、現在では簡単に様々な情報にアクセスできます。
特に、学校のテストで時事問題が出題されることがあり、迅速に情報を得ることができるのは大きなメリットと言えるでしょう。
学習のサポート
スマートフォンを使えば、何か疑問が浮かんだときにすぐに調べて解決策を見つけられることが、非常に便利です。
以前は、疑問に答えを見つけるためには図書館で本を探したり、資料を読み漁る必要があり、時間も労力もかかっていました。
また、インターネット上には無料で利用できる教育コンテンツが豊富にあり、追加の費用をかけずに新しい知識を得ることができます。
インターネットの情報は質にばらつきがあるため、情報を選ぶ際には慎重になる必要がありますが、賢く使えば学習の強力なサポートとなります。
位置情報での安心
スマートフォンには位置情報サービスやメッセージ機能があり、自分のいる場所や何をしているのか、いつ家に帰るかを簡単に家族に伝えることができます。
たとえば、部活動が予定より遅くなったり、急な悪天候で帰宅が遅れたりしたときでも、すぐに現在の状況を伝えられるため、家族を安心させることができます。
特に、災害などの緊急事態が発生した時には、速やかに情報を得て家族と連絡を取ることができるのは、非常に心強いです。
コミュニケーションの手段として
今日では、ソーシャルネットワーキングサービス(SNS)が子供たちの間で広く使われています。
スマートフォンは、これらのコミュニケーションを取るための非常に有効な道具です。
例えば、中学時代に友達と交換したLINEのIDは、高校生活やその後もずっと連絡手段として使い続けることができます。
たとえ連絡先を変更したとしても、一度つながってしまえば、容易に関係が途切れることはありません。
昔に比べ、直接会う機会が少ない友達とも長く繋がっていられるのは、現代ならではのメリットです。
友達だけでなく、家族間のコミュニケーションもよりスムーズで密になります。
たとえば、家族間でLINEのグループを作り、予定を共有したり管理したりする家庭も少なくありません。
中学生のスマホ利用に伴うデメリットとトラブル
スマホが便利な存在であることに疑いはありませんが、中学生がこれを使う際には、メリットだけではなく、様々な問題やトラブルが伴うことも理解しておく必要があります。
これらの点をきちんと把握して、注意深く見守りましょう。
金銭的なトラブル
スマートフォンでアプリを使う時、最初は無料でも後で追加の支払いが必要になるゲームがあります。よくあるケースとして、親のクレジットカードを登録してしまい、後で気軽に課金してしまうことがあります。
大人でも同じようなトラブルに遭遇することがあり、広告をクリックしただけで不正な請求を受けるリスクもあります。スマホを持つことに伴う金銭的なリスクは見過ごせません。
デジタル依存症
SNSやLINEへの過度な依存は、睡眠不足やお風呂場にスマホを持ち込むなどの問題を引き起こします。
スマホが手元にないと落ち着かない、食事中や朝起きた直後にもスマホを確認する習慣が根付く恐れがあります。
ネットいじめの問題
インターネット上でのいじめはますます深刻化しています。ネットいじめが原因での自傷行為や自殺がニュースになることも少なくありません。
スマホを介してインターネットに繋がることで、子どもがいじめの被害者や加害者になる可能性があります。
知らない人からの接触の危険性
ある知人の話ですが、その中学生の娘さんがオンラインでバンドメンバーを募集した際、別の意図を持つ年上の男性から応募がありました。
これはスマホを使って気軽に写真や動画を共有することの副作用で、新しい友達を作るチャンスがある反面、悪意を持った見知らぬ人から接触されるリスクもあるということです。
中学生へのスマホを持たせる時に考慮すべきこと
使用に関するルール設定
中学生はまだ義務教育期間中で保護者の管理下にあるため、スマホ使用に関する家庭でのルール作りが必要です。
例えば、「食事中はスマホをいじらない」「大切な話をしている時は、通知があってもスマホを見ない」などのルールが考えられます。
リスクについての話し合い
スマホを使う上でのリスクや問題点を、子供とあらかじめ話し合うことが重要です。
上述したようなリスクを例に挙げて、その内容をしっかり説明しましょう。
この時、あなたが心配しているからこそ伝えていることを、子供にしっかりと理解してもらうことが大切です。
課金を防ぐ設定
iPhoneや他のスマートフォンでは、課金を防ぐ設定ができます。
この機能を事前に設定しておけば、子供たちも安心してゲームやアプリを楽しめます。
コンテンツ制限を設ける
インターネット上には成人向けのコンテンツも含め、さまざまな情報があふれています。
子供が不適切なサイトにアクセスしないように、コンテンツフィルタリング機能の活用がおすすめです。
携帯電話会社の多くがフィルタリングサービスを提供しているため、どのようなサービスが利用できるか確認してみると良いでしょう。
中学生のスマホ利用に関する家庭での話し合い
子どもにスマホを持たせるべきかどうかは、そのメリットとデメリットをしっかり理解した上で、家族でよく話し合い、決めるべきことです。
子どもの意見も重要ですから、彼らがどう思っているかを聞くことを忘れないでください。
現在、高校生の多くがスマホを持っています。そのため、単純に年齢だけで決めるのではなく、適切な使用ルールを設定し、保護者がデバイスやインターネットの安全設定を事前に行うことで、中学生でも安全に使用できます。
私の知り合いの保育園では、上のクラスの子どもがスマホを持っていました。
その理由を母親に聞くと、習い事の時間変更など、子ども自身が情報を直接受け取るためだそうです。
また、移動時間に学習アプリで遊ぶことも許可しているとのことです。
私は、家族が必要だと感じた時に、年齢に関わらずスマホを持たせることを良いと思います。
その時は、ルールをしっかり設け、依存しないように適切に使い方を指導したいですね。