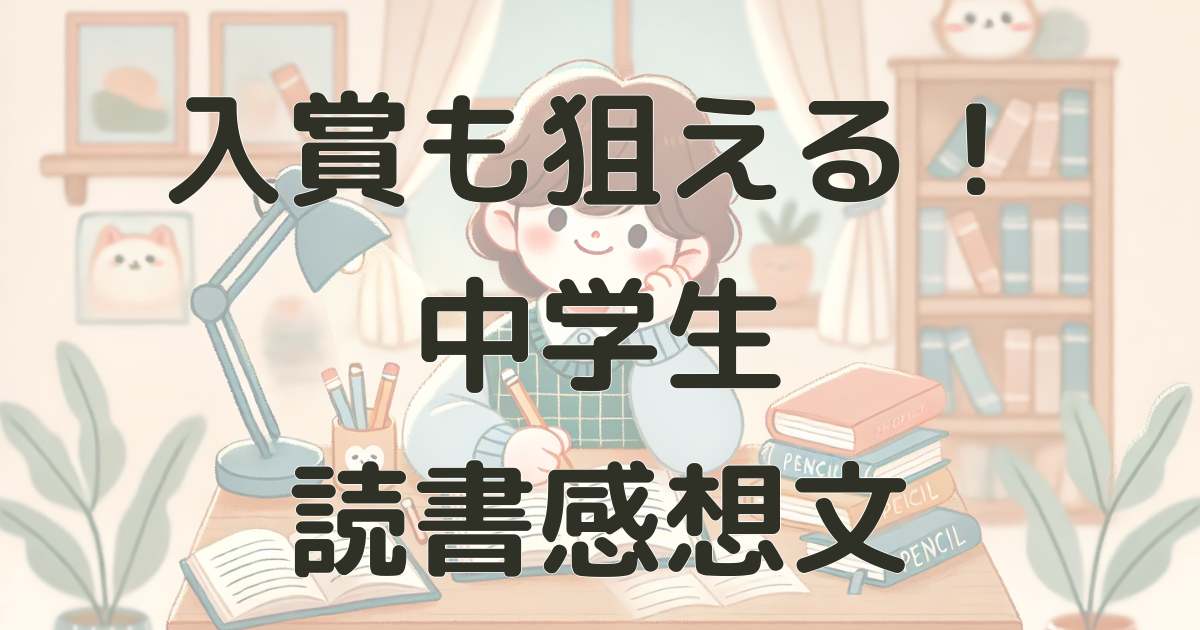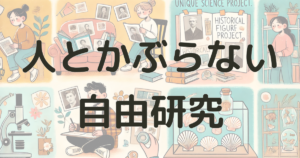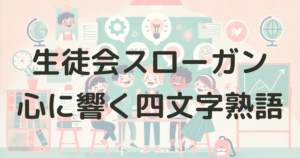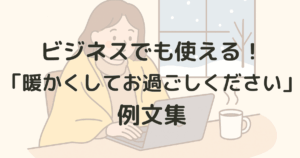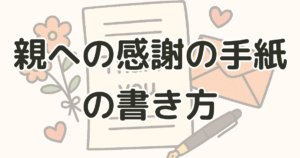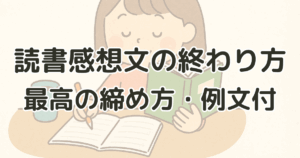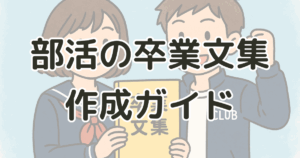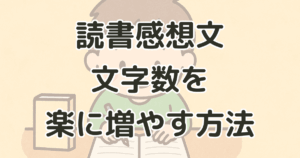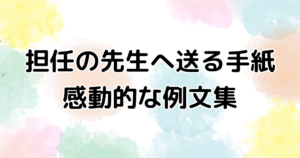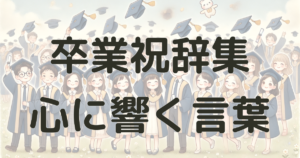「読書感想文って、何を書けばいいのかわからない……。」
そんな悩みを持つ中学生の皆さんへ、本記事では読書感想文の書き方をわかりやすく解説します。
ただのあらすじ紹介ではなく、どのように自分の感想を深め、魅力的な文章に仕上げるかを丁寧に説明していきます。
本の選び方から構成の作り方、共感を呼ぶ表現の工夫、さらには感想文を見直す際のポイントまで、すぐに役立つ実践的なテクニックを紹介。
原稿用紙の正しい使い方や、過去の優れた作品を参考にする方法まで幅広くカバーしています。
感想文は決して難しいものではありません。
自分の気持ちを素直に表現し、ちょっとした工夫を加えるだけで、読み手の心に響く文章が書けるようになります。
この記事を読めば、感想文を書くことが楽しくなり、コンクールで入賞を目指すことも夢ではありません。
あなたも、読書感想文の書き方をマスターし、自信を持って素晴らしい作品を仕上げてみませんか?
さっそく、具体的なポイントを見ていきましょう!
読書感想文の書き方とは?
中学生向けの基本的な書き方
読書感想文は、読んだ本についての感想をまとめる文章です。
単にあらすじを紹介するだけではなく、本を読んで感じたことや考えたことを自分の言葉で書くことが大切です。
中学生にとっては、感想文を通じて論理的な文章の書き方を学ぶ良い機会でもあります。
読書感想文の重要なポイント
- 本の選び方 – 自分が興味を持った本を選ぶことで、より深い感想を書きやすくなります。
- あらすじを簡潔にまとめる – あまり長くなりすぎないように、物語の流れを簡潔に説明します。
- 感想を具体的に書く – どの場面でどんなことを感じたのか、具体的な理由を交えて書くと説得力が増します。
- 読んだ本から学んだことを述べる – 自分の成長や考え方の変化を説明すると、より深みのある感想文になります。
感想文を書く際の注意点
- あらすじだけにならないようにする
- 他人の感想をそのまま書かない
- 誤字脱字をなくし、読みやすい文章にする
- 感情を素直に表現する
読書感想文の構成を理解する
具体的な段落の構成
- 導入(本を選んだ理由や簡単な紹介)
- あらすじ(短めにまとめる)
- 感想(本を読んで感じたこと)
- 結論(本から学んだこと、今後の考え方への影響)
あらすじを効果的に紹介する方法
- 物語の主な流れを簡潔に書く。
- 登場人物や設定に触れる。
- 物語のクライマックスに軽く触れるが、結末は詳しく書きすぎない。
感想部分の書き方のコツ
- 印象に残った場面を具体的に取り上げる。
- 自分の経験と関連付ける。
- 本を読んだ後の気持ちの変化を述べる。
魅力的な書き始めのテクニック
インパクトのある書き出し
- 質問を使う:「もしあなたがこの本の主人公だったら、どうしますか?」
- 驚きを表す表現:「私はこの本を読んで、予想もしない驚きを感じました。」
主人公やテーマを引き出す言葉
- 「この本の主人公○○は、私にとってとても共感できる存在でした。」
- 「この本のテーマは『友情』であり、その大切さを改めて考えさせられました。」
読者の興味を引く方法
- 感情を込めた表現を使う:「この場面では涙が止まりませんでした。」
- 結論を最初に示す:「この本は、私の人生観を変える一冊でした。」
感想文に必要な要素とは?
作品選びのポイント
- 自分が興味のあるジャンルの本を選ぶ。
- 感動したり、考えさせられる本を選ぶ。
- 物語の長さや難易度も考慮し、最後まで読み通せる本を選ぶ。
- できれば、自分の経験と重なるテーマを持つ本を選ぶと、より深い感想を書きやすい。
- コンクールに応募する場合は、評価されやすいテーマの本を選ぶのも一つの方法。
テーマを掘り下げる考え方
- 本の中で扱われるテーマ(友情、家族、勇気など)を考える。
- そのテーマが自分の経験とどのように関わるかを考える。
- 例えば、「友情」がテーマなら、自分の友人関係と比較してみる。
- 「家族」がテーマの場合、自分の家族との関係性を振り返りながら感想を述べる。
- 物語の中で登場人物がどのように成長し、どのような変化を遂げたかを考察する。
- テーマが社会的な問題と関連している場合、その問題について調べて自分なりの考えを加えると深みが増す。
著者の意図を理解する方法
- 物語の背景や設定を調べる。
- 著者が伝えたいメッセージを考える。
- 著者の経歴や執筆の動機を調べると、作品の意図をより深く理解できる。
- 例えば、戦争をテーマにした本なら、その時代背景を調べることでより内容が理解しやすくなる。
- インタビューやあとがきがある場合は、それを読んで著者の考えに触れる。
- 他の作品と比較して、著者が一貫して持っているメッセージを探ると、感想の幅が広がる。
入賞作品の分析
- どのような表現が使われているかを分析する。
- 文章の構成や流れを参考にする。
- 受賞作品の書き出しや結論の書き方を比較し、共通点を見つける。
- 感情をどのように表現しているかを詳しく読み取り、真似できるポイントを探す。
- 物語のどの部分に焦点を当てているかを考察し、自分の感想文にも応用する。
- 過去のコンクール作品を読むことで、審査員の評価基準を理解する。
- 短めの文章で、初心者にも書きやすい例を示す。
読書感想文の具体例
簡単な本の感想文例
読書感想文を書く際、初心者にとって一番のハードルは「何を書けばよいのか分からない」ことです。
そこで、シンプルな感想文の例を示します。
例文:
『走れメロス』を読んで
私はこの本を読んで、友情の大切さについて考えさせられました。
主人公のメロスは親友を救うため、命がけで約束を守ろうとします。
その姿に感動し、自分も友達との約束をもっと大切にしようと思いました。
特に、メロスが力尽きそうになりながらも走り続ける場面では、心が熱くなりました。
友情とは、簡単に諦めるものではなく、努力して守るものなのだと感じました。
このように、簡単なあらすじと、自分の感想を交えて書くことで、シンプルながらもまとまりのある感想文になります。
マンガの感想文の書き方
マンガの感想文を書く際には、普通の小説と違うポイントがあります。
- ストーリーの面白さだけでなく、絵の表現や演出についても触れる
- セリフやコマ割りの工夫が物語にどう影響しているか考える
- キャラクターの表情や動作から読み取れる感情に注目する
- 自分が特に心に残ったシーンを具体的に述べる
例えば、『スラムダンク』の場合、
「試合中の迫力ある描写がまるで実際の試合を見ているようだった」
「桜木花道の成長が目に見えて分かり、最初の未熟な姿との対比が感動的だった」など、
マンガならではの特徴を取り上げると、より深い感想文になります。
感情を伝える表現の仕方
共感を呼ぶ言葉選び
感想文では、自分の感じたことを読者に伝えるために、共感を呼ぶ言葉を選ぶことが重要です。
例えば、「私も同じような経験をしたことがあります」と書くと、読み手も「そういうことあるよね」と共感しやすくなります。
また、「この場面で涙が止まりませんでした」「読んでいて心が温かくなりました」のように、感情を素直に表現することで、文章に臨場感が生まれます。
具体的なエピソードを盛り込む
感想文の中で、自分の経験と本の内容を関連付けると、より説得力のある文章になります。
例えば、『ごんぎつね』を読んで、「私も過去に誤解されてしまったことがあり、そのときの気持ちがよく分かりました」と書けば、読者はより深く共感できます。
また、「この本を読んだ後、家族ともっと話をするようになりました」など、自分の行動や考え方にどのような変化があったかを書くと、より具体性が増します。
印象に残るセリフの使い方
本の中の印象に残ったセリフを引用し、それについて自分の意見を述べると、感想文に説得力が増します。
例えば、『銀河鉄道の夜』の「ほんとうのさいわいとはなんだろう」というセリフについて、「この言葉を読んで、本当の幸せについて深く考えさせられました」と書けば、考察が深まります。
作成した感想文の見直し
改行や構成のチェック
感想文を書いた後は、読みやすいかどうかを確認しましょう。
- 段落ごとに意味がまとまっているか
- 1つの文が長すぎないか
- 改行を適切に使っているか
読みやすい文章は、内容が伝わりやすくなります。
友人や保護者に見てもらう
書いた感想文を他の人に読んでもらうと、新しい視点での意見をもらうことができます。
例えば、「この部分、もう少し詳しく書いたほうがいいよ」など、具体的なアドバイスがもらえるかもしれません。
必要な修正ポイント
- 誤字脱字がないかチェックする。
- 文章の流れがスムーズか確認する。
- 本当に自分の感想が書かれているか見直す。
感想文を書く際のマスの使い方
原稿用紙のレイアウト
原稿用紙を使う場合、以下のルールに注意しましょう。
- 1行目の最初のマスを空ける。
- 句読点はマスの右上に小さく書く。
- 改行する際は、適切な場所で行う。
紙面の活用法
- 余白を活かし、詰め込みすぎないようにする。
- 段落ごとに適切なスペースを確保する。
視覚的に分かりやすくする方法
- 重要な部分は短く区切る。
- 難しい言葉の説明を加える。
読書感想文を書くための勉強方法
過去の作品を参照する
過去に入賞した感想文を読むことで、良い書き方の例を学ぶことができます。
例えば、コンクールの入賞作品を読むと、「どのように感想を書けば良いか」「どんな言葉を使えば伝わりやすいか」などのヒントを得ることができます。
コンクールの例を参考にする
コンクールで評価される感想文には、以下の特徴があります。
- 読んだ本のテーマをしっかり考察している。
- ただのあらすじではなく、自分の意見がしっかり述べられている。
- 説得力のある文章で、感情が伝わりやすい。
同じテーマで比較する手法
例えば、「家族愛」をテーマにした本を複数読み、それぞれの作品がどのように家族愛を描いているかを比較すると、より深い感想文が書けます。
このように、読書感想文の書き方を工夫することで、より魅力的な文章を作成できます。
まとめ
読書感想文を書くことは、単に本の内容をまとめるだけではなく、自分の考えや感じたことを表現し、深く思考する力を養う大切な作業です。
適切な本を選び、効果的な構成を意識しながら、自分の感情を素直に伝えることで、より魅力的な感想文を書くことができます。
また、推敲や見直しを丁寧に行うことで、読みやすく、説得力のある文章に仕上げることができます。
重要なポイント
- 本の選び方:自分の興味のある本や、テーマが身近な本を選ぶと感想が書きやすい。
- 感想文の構成:導入、あらすじ、感想、結論の流れを意識して書く。
- あらすじの書き方:短くまとめ、物語のクライマックスや重要な出来事に焦点を当てる。
- 感想の書き方:印象に残った場面を挙げ、自分の経験や考えと関連付ける。
- 共感を呼ぶ表現:感情を素直に伝え、具体的なエピソードを交えて書く。
- セリフの活用:印象的なセリフを引用し、それに対する自分の考えを述べる。
- 改行や構成のチェック:段落のバランスや文の流れを見直し、読みやすくする。
- 第三者に読んでもらう:友人や保護者に見てもらい、改善点を把握する。
- 原稿用紙の使い方:適切なレイアウトで、視覚的に分かりやすい文章にする。
- 過去の優れた作品を参考にする:入賞作品の構成や表現を学び、自分の文章に活かす。
- 比較する手法を使う:同じテーマの本を比べることで、より深い考察を加える。
読書感想文は、ただ義務的に書くものではなく、自分の成長や学びにつながる貴重な機会です。
しっかりと準備し、自分の思いを丁寧に表現することで、より質の高い感想文を書くことができるでしょう。