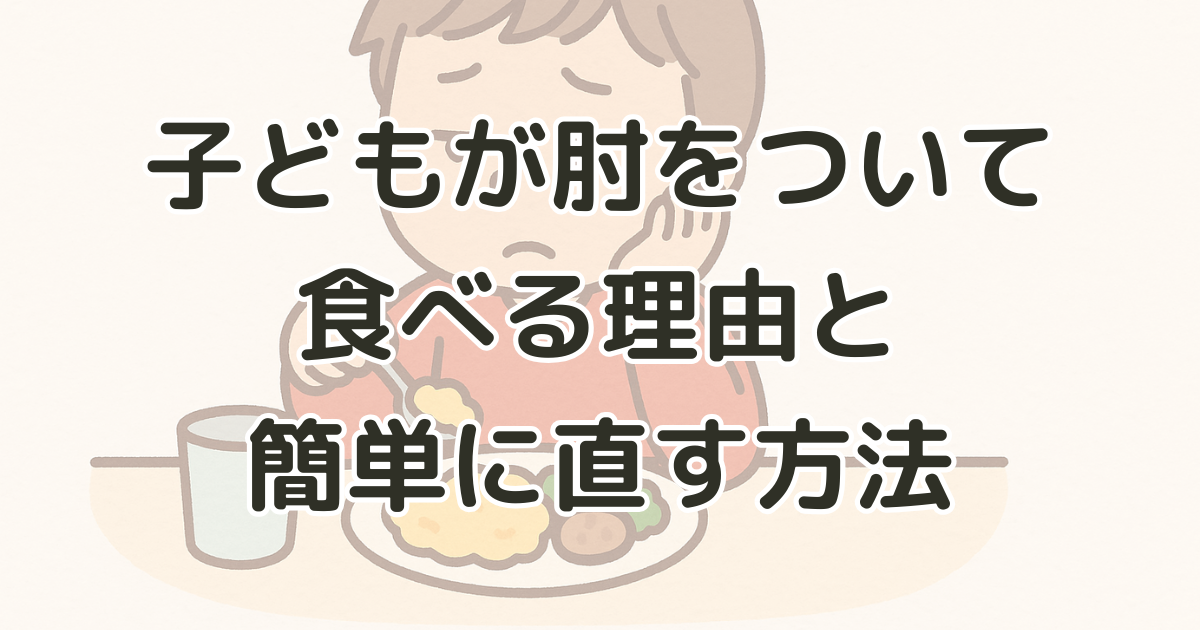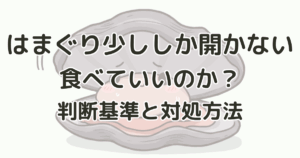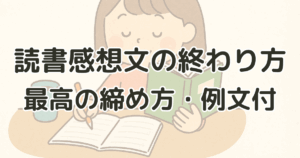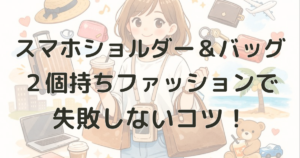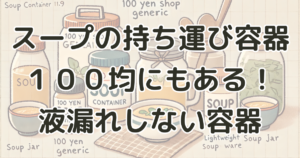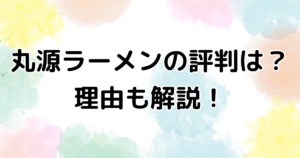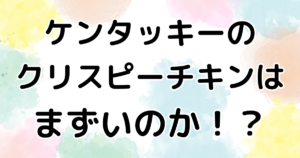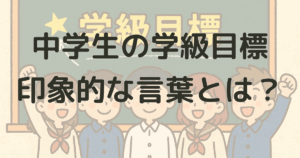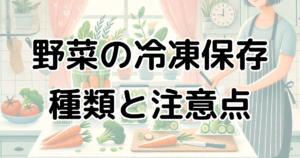こんにちは!子育て中の皆さん、お子さんの食事中の姿勢について、ふと気になることはありませんか。
特に「肘をついて食べる」という行動は、多くのご家庭でよく見られる光景かもしれませんね。
なぜ子どもは肘をついてしまうのか、そしてどうすれば優しく直してあげられるのか、今回はそんな疑問にお答えしていきます。
子どもが肘をついて食べる理由
お子さんが食事中に肘をついてしまうのには、いくつかの理由が考えられます。
大人の私たちから見ると「行儀が悪い」と感じてしまいますが、子どもには子どもなりの事情があるのかもしれませんね。
文化的背景と食事マナーの違い
食事のマナーは、国や文化によって大きく異なります。
日本では「肘をついて食べるのは行儀が悪い」とされていますが、海外ではそこまで厳しくない国もあります。
例えば、中東の一部地域では、食事中に片肘をつくのが自然な姿勢とされることもあります。
このように、私たちが当たり前だと思っているマナーも、実は文化的な背景に根ざしていることが多いのです。
子どもたちは、まだそうした社会的なルールや文化的な背景を十分に理解していません。
家庭で教えられたことが全てであり、外の世界のマナーとの違いを認識する機会も少ないでしょう。
そのため、無意識のうちに楽な姿勢を選んでしまうのです。
肘をついて食べる心理とは?
子どもが肘をついて食べる心理には、いくつかの要因が考えられます。
- 楽な姿勢だから。食事中に疲れてしまったり、体が小さくてテーブルとの距離が合わなかったりすると、無意識のうちに肘をついて楽な姿勢を取ろうとします。特に、長時間座っていることに慣れていない小さなお子さんにはよく見られます。
- 集中しているから。食事に夢中になっていると、周りのことや姿勢にまで意識が回らないことがあります。目の前の食べ物に集中しすぎて、つい前のめりになり、肘がテーブルについてしまうのです。
- テーブルの高さが合っていないから。子どもの身長に対してテーブルや椅子の高さが合っていない場合、姿勢が安定せず、肘をついて体を支えようとすることがあります。
- 習慣になっているから。家庭内で誰も注意しない、あるいは家族の誰かが肘をついて食べているのを見て真似をしているうちに、それが当たり前の習慣になってしまうこともあります。
行儀が悪いとされる理由
では、なぜ日本では肘をついて食べるのが「行儀が悪い」とされるのでしょうか。
- 見た目の問題。肘をついていると、だらしない印象を与えがちです。特に食事の場では、一緒に食事をする人への配慮が求められます。
- 衛生面の問題。食事中に肘をつくと、服の袖が食べ物に触れたり、テーブルの上の食べ物を邪魔したりする可能性があります。また、手元が不安定になり、食器を倒してしまうリスクも高まります。
- 健康面の問題。長時間肘をついた姿勢で食事をすると、消化に良くなかったり、姿勢が悪くなったりすることもあります。猫背になりやすく、体の歪みにつながる可能性も指摘されています。
これらの理由から、日本では食事中の肘つきは避けるべき行為とされているのです。
肘をついて食べるが日常的な習慣
肘をついて食べる行動が、いつの間にか日常的な習慣になってしまうこともあります。
特に子どもの場合、一度身についた習慣を変えるのは少し時間がかかるかもしれません。
肘をついて食べる子どもの特徴
肘をついて食べる子どもには、以下のような特徴が見られることがあります。
- 体が小さい子。まだ体が小さく、テーブルや椅子の高さが合っていない場合に、体を支えるために肘をついてしまうことがあります。
- 集中力が高い子。食事に夢中になると、周りが見えなくなり、姿勢がおろそかになることがあります。
- 疲れている子。遊び疲れていたり、眠かったりする時に、楽な姿勢を求めて肘をつくことがあります。
- 注意された経験が少ない子。家庭内で肘つきについて特に注意されたことがない場合、それが悪いことだと認識していないことがあります。
家庭での肘をついて食べる習慣
家庭は、子どもが最初に社会性を学ぶ場所です。
食事のマナーも、家庭での習慣が大きく影響します。
- 家族の習慣。もし家族の中に肘をついて食べる人がいると、子どもはそれを見て真似をしてしまうことがあります。子どもは親や周りの大人の行動をよく見ていますから、大人が手本を示すことが大切です。
- 食事環境。食卓の雰囲気も影響します。忙しくてゆっくり食事ができない、テレビを見ながら食事をするなど、食事に集中しにくい環境だと、姿勢がおろそかになりがちです。
- 注意の仕方。肘つきを注意する際に、感情的に怒鳴ったり、一方的に叱ったりすると、子どもは反発したり、食事自体が嫌いになったりする可能性があります。優しく、しかし継続的に伝えることが重要です。
友人やレストランでの行動
家庭での習慣は、外での行動にもつながります。
- 友人との食事。友人との食事中に肘をついていると、周りの子に真似されたり、親御さんから「あの子は行儀が悪い」と思われたりする可能性もあります。
- レストランでの行動。レストランのような公共の場では、周囲の目も気になります。肘をついて食べていると、お店の雰囲気にもそぐわず、他のお客さんに不快感を与えてしまうこともあります。
子どもが社会に出たときに困らないよう、家庭でしっかりとしたマナーを身につけさせてあげたいですね。
肘をついて食べることの影響
肘をついて食べることは、単なるマナー違反だけでなく、さまざまな影響を及ぼす可能性があります。
他人への印象とマナー違反
まず、最も分かりやすいのが「他人への印象」です。
- だらしない印象。肘をついて食事をしている姿は、だらしなく見えがちです。特に初対面の人や目上の人との食事の場では、相手に不快感を与えてしまう可能性があります。
- 育ちが悪いと思われる可能性。「食事のマナーがなっていない」と判断され、その子の育ち方まで評価されてしまうこともあります。これは、子どもが将来、社会で円滑な人間関係を築く上で不利になることも考えられます。
- 一緒に食事をする人への配慮不足。食事の時間は、一緒にいる人とのコミュニケーションを深める大切な時間です。肘をついていると、会話中に相手の目を見て話すことが難しくなったり、食事への集中が欠けているように見えたりして、相手への配慮が足りない印象を与えてしまいます。
食事の時間における所作の重要性
食事の時間は、単に栄養を摂るだけでなく、心身を整え、感謝の気持ちを育む大切な時間でもあります。
- 集中力の向上。正しい姿勢で食事をすることで、食べ物に意識が向きやすくなり、集中して味わうことができます。これは、味覚の発達にもつながります。
- 消化の促進。良い姿勢で食事をすることは、消化器官への負担を減らし、消化を促進する効果も期待できます。
- 感謝の気持ちの育成。食事の準備をしてくれた人や、食材への感謝の気持ちを育む上でも、丁寧な所作は大切です。マナーを守ることは、相手への敬意を示すことにもつながります。
- 美しい姿勢の習慣化。食事中の姿勢を意識することは、日常生活全体の姿勢を良くすることにもつながります。子どもは成長期に体の基礎が作られるため、早い段階で正しい姿勢を身につけることは非常に重要です。
肘をついて食べるの直し方
お子さんの肘つきを直すのは、根気が必要ですが、いくつかのポイントを押さえれば、きっと改善できます。
優しく、そして楽しく教えてあげましょう。
簡単に実践できる食事姿勢改善法
日常生活で簡単に取り入れられる方法をご紹介します。
- テーブルと椅子の高さを調整する。まずは、お子さんの体格に合ったテーブルと椅子を用意することが大切です。足がブラブラしないように、足置きがある椅子を選ぶか、足元に台を置くなどして、安定した姿勢で座れるようにしてあげましょう。
- 「おへそはテーブルに」の合言葉。食事の前に「おへそはテーブルに近づけてね」と声をかけると、自然と体が前に傾きすぎず、背筋が伸びた姿勢になります。
- 食事の前に手を膝に置く習慣。食事が始まる前に「おてては膝の上ね」と声をかけ、手を膝に置く習慣をつけると、肘がテーブルにつくのを防げます。
- 食事に集中できる環境を作る。テレビを消す、おもちゃを片付けるなど、食事に集中できる環境を整えましょう。気が散るものが少ないと、自然と姿勢も意識しやすくなります。
- 短時間から始める。最初から完璧を求めず、まずは数分だけでも正しい姿勢を意識させることから始めましょう。少しずつ時間を延ばしていくと良いでしょう。
子どもに教えるテーブルマナー
肘つきだけでなく、食事全体のマナーを教える良い機会です。
- 具体的に伝える。「肘をつかないで」と言うだけでなく、「お膝に手を置いて、背筋をピンと伸ばして座ろうね」など、具体的にどうすれば良いかを伝えてあげましょう。
- 理由を優しく説明する。「肘をつくと、お料理が食べにくくなっちゃうよ」「みんなが気持ちよくご飯を食べるために、きれいに座ろうね」など、子どもにもわかる言葉で理由を説明してあげると、納得しやすくなります。
- 褒めて伸ばす。少しでも良い姿勢で食べられたら、「上手に座れたね!」「きれいな姿勢で食べられて素敵!」とたくさん褒めてあげましょう。褒められることで、子どもは自信を持ち、次も頑張ろうという気持ちになります。
- 大人が手本を示す。何よりも大切なのは、大人が良い手本を示すことです。家族みんなで正しい姿勢を心がけ、食事のマナーを大切にする姿を見せましょう。
- 絵本や動画を活用する。食事のマナーに関する絵本を読んだり、動画を見たりするのも良い方法です。楽しみながらマナーを学ぶことができます。
まとめ:子どもの食事マナーを育てるために
お子さんの食事中の肘つきは、多くの親御さんが悩むことの一つです。
しかし、その理由を理解し、根気強く、そして愛情を持って接することで、きっと良い方向へと導くことができます。
根本的な理由と実践すべきこと
- 肘つきの根本的な理由:
- 体の発達段階や体格に合わない環境。
- 疲れや集中力の欠如。
- 習慣化や周りの大人の影響。
- 実践すべきこと:
- 食事環境の整備。テーブルや椅子の高さを調整し、足元を安定させる。
- 具体的な声かけ。「おへそはテーブルに」「おてては膝の上」など、わかりやすい合言葉を使う。
- 褒めて伸ばす。良い姿勢で食べられたら、積極的に褒めて自信をつけさせる。
- 大人が手本となる。家族みんなで正しい食事マナーを実践する。
今後の習慣形成に向けたアドバイス
食事のマナーは、一度教えたら終わりではありません。
日々の積み重ねが大切です。
- 焦らない。子どもがすぐに完璧になることはありません。少しずつ、できることを増やしていく姿勢で臨みましょう。
- 継続する。毎日少しずつでも良いので、意識して声かけを続けましょう。
- 食事の時間を大切にする。食事は家族のコミュニケーションの場でもあります。マナーを教えるだけでなく、楽しく会話をしながら、温かい食事の時間を過ごすことを心がけましょう。
お子さんが将来、どんな場所でも自信を持って食事ができるよう、今から一緒に素敵な食事マナーを育んでいきましょうね。